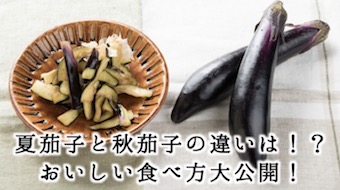幻の大和野菜「祝だいこん」。作り継がれるその理由とは。

古の都・奈良県には平城京に遷都された710年よりも古くから伝わる”大和野菜”がたくさんあります。味も美味な野菜が多く、地元では祝事や客人をもてなす料理に使われることが多いです。
そんな古都・奈良のお膝元、奈良県奈良市に伝わる「祝だいこん」(いわいだいこん)はご存知でしょうか。
この記事では、大和野菜の中でもあまり知られていない、祝だいこんについて詳しく説明いたします。
祝だいこんとは?

出典元:奈良県公式ホームページより
祝だいこんとは、四十日大根から系統を分けている大根です。
奈良県では主に正月の雑煮用として栽培されています。
その由来は日本書紀に”於朋禰(おほね)”と記載されているほど古く、昔から人々の食生活に息づいてきました。
一般家庭向けの栽培は大正時代から本格的に始まり、2005年に大和の伝統野菜として奈良県より”大和野菜”に認定されました。これを機会に奈良県内で呼ばれていた「雑煮だいこん」から「祝だいこん」と名付けられました。
雑煮だいこんという昔の名前からもわかるように、新年を迎える雑煮の準備で年末需要が高い野菜ですが、収穫してから市場に出回る時期が年末(12月下旬)の数日のみという非常に珍しい野菜でもあります。
栽培は10月中旬頃から種を蒔き始め、同月末頃には間引きをします。(間引いただいこんの葉も出荷されています。)
そして12月に収穫、出荷がされます。
この期間内は奈良県内のスーパーに設けられている地元野菜コーナーや八百屋で購入することができますが、それ以外の時期に市場に出ていることはほとんどありません。
祝だいこんの味や特徴
実はこの祝だいこん、スーパーに並んでいる私たちが知る大根とは見た目が少し異なります。
とにかく「細い」のです。
長さが20~30cmに対し、直径が約3cmとスラっとした細身です。
主食部分の根は成長過程で曲がりやすいため、栽培時には丁寧に土寄せをして柔らかい土壌を準備する必要があり、大量生産が難しい野菜です。
丁寧に育てられた祝だいこんは肉質がしっかりと締まっていて、雑煮にしても煮崩れがしにくく、歯ごたえのあるコリっとした食感を楽しむことができます。
味も大根らしい爽やかな味で良く煮汁を吸ってくれるので煮物に適しています。
祝だいこんを使った料理
正月に欠かせない野菜として、作り継がれてきた祝だいこん。どんな料理で食べられることが多いのでしょうか?
大和の雑煮
奈良県(大和地方)の雑煮は円満(夫婦や家庭などたくさんの円満があります)の願いを込めて野菜を”輪切り”にします。
また里芋や豆腐も丸く形を整えて、さらに焼いた丸餅を加えます。そして、最後に丸い食材に満たされた食材を白味噌で仕立てて雑煮にします。
雑煮に付ける一品として祝だいこんの葉を炒めると食卓の色合いも良くなりますし、おいしく食べられます。また、おひたしやチャーハンの具材としても美味です。
そんな祝だいこんは雑煮のお椀のサイズにぴったりと合うことから”雑煮の友”として重宝されてきました。
祝だいこんご飯
正月に珍重される祝だいこんですが、その細かさを生かして炊き込みご飯にすると、また違う魅力を味わうことができます。
味が染み込みやすく、肉質が締まっているのでご飯と一緒に炊き込んでも、その存在をしっかり感じることができます。
他の野菜も大きさを合わせて切りそろえることで、食感が整って食べやすくなります。
祝だいこん 仕入れ先の紹介
西喜商店

京都で創業90年余りを誇る八百屋です。京都府内はもちろん、全国発送も受け付けています。祝だいこんは一年に一度しか入荷できないため、仕入れの際は先に問い合わせすることがおすすめです。
Oisix

できるだけ農薬を使わない栽培方法で育てられている、減農薬の祝だいこんを購入することができます。収穫時期が限られているため購入の際は、サイトを細目にチェックする必要があります。
結びに
いかがでしたか?「円満」の想いを込めて、縁起の良い食材として正月料理に使われてきた、祝だいこん。大和野菜の一つとして、丁寧に作り継がれてきました。
大量生産が難しいため、市場に出回る数が少なく、全国的にはまだ知られていない食材です。
自店舗でも、ぜひ縁起のよい祝だいこんを、正月メニューとして取り入れてみてはいかがでしょうか?